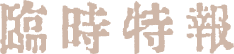「自分が今持っている能力の中で一番高いものを売ろう」と思った。
元デートクラブ嬢が当時の仕事の話する
「彼女」という存在
私は毎月決まった額を恋人の口座に振り込み、そして時々彼と会った。
それまでバリバリと仕事をこなし、業績を上げてきた彼は、痛みで自分が思うように動けないことが苦痛で仕方ないようだった。
私はこのことにとても驚いた。女性であれば、働いているうちに、月のものでどうしようもなく体調が悪くても、だましだまし仕事をすることに慣れてしまうようなところがある。
極端に言えば、月の1/4は、万全な状態でなどあり得ないという前提で働いていた。
それとは違う前提で生きてきて、苦しんでいる恋人を見るのは辛かった。私自身が甘えた前提で生きてきたような気もした。
恋人と会った後に急いで汐留のホテルに向かい、お客さんの背広をハンガーに掛けながら、私は突然気づいた。
そうか、この人達はただただ純粋な「彼女」という存在が欲しいんだ。
学生時代に付き合う彼女みたいに、何のしがらみも利害関係もなく話せる相手。
日常の中で押し着せられている、部長だとか専務だとか夫だとか父だとかいう役割の衣を脱ぎたい、そのためになら一晩で10万20万のお金を遣ったって構わないんだ。
世間ってなんだろう、と私は考えた。
私も大概世間知らずだけど、彼らが日常を過ごしている「世間」は、痛みもなくバリバリ仕事をこなせることが当たり前、お金をつぎこんででも、自分を安らかに保ってくれる「彼女」にいてもらうのが良しとされる世界なのだ。
それはとても偏っていると思った。
そんなことを全く知らずに生きてきた私の「世間」と、もしかしたら同じ程度に偏っているかもしれないとさえ思った。
そうこうするうちに、昼間に勤めていた会社で昇進が決まった。会社への責任が重くなることを考えて、私はデートクラブを退会することにした。恋人には「今までのようにあなたを支えることが出来なくなった」とだけ伝えて連絡を絶った。何度も泣くうちに、ひょんなことからかつてのお客さんをSNSで発見した。名前も会社名も生活ぶりも全部ダダ漏れだった。自分は正しい選択をしたのだ、と思い、涙を拭いた。
デートクラブ嬢をしていた約1年の間に、私は、「何かをすること」ではなく「何かであること」に対して値段を付けることのあぶなっかしさと難しさを知ったと思う。お客さんはみな善良で、不器用で、淋しい人達だった。多少の差はあれ、誰でもそうであるように。
私のお客さんは、沢山いるデートクラブ嬢の中から私を選んで、その淋しさを見せてくれて、ちゃんとお金を払ってくれた。二度と会うことはないけれど、そのことにはとても感謝している。
その数年後、「何かをすること」の価値を真っ向から否定して、盗みを繰り返す男の子を拾ってしまうことになるのだけど、それはまた、別のお話。
機会があればまた、綴ろうと思う。