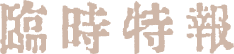山の子をその手に抱き、美しき山姥は笑う。
神々と寝た女 ~逢魔が時の過ぎぬ間に Vol.3 金太郎の母
「まさかりかついだ金太郎」――
彼がどうして生まれ、なぜ伝説になったのか、意外に知られていません。
金太郎は山姥と龍の間に生まれた子どもである、とする昔話が伝わっています。
その出生には、日本の成り立ちと山の民とに関わる、ある物語が隠されています。
金太郎の動きはゆったりとしているように見えて、その歩みは早かった。歩きにくい山の森の中であるにも関わらず、まるで均した路を行くようにすいすいと進んでいくのだ。頼光はその後を追うのがやっとだった。
しばらく追ったが、金太郎の後ろ姿は森の闇に紛れ、見えなくなってしまった。頼光は辺りを見回す。樵ともはぐれてしまっていた。山の中では方角もわかりはしない。
迂闊なことをした自らの身を恥じ入るが、後悔しても仕方がなかった。とりあえず、山を降りる方にあたりをつけて歩き出す。しかし、下りと見えた道はいつの間にか登りへと転じ、登りと見えれば岩や川に遮られ、帰る道はようとして知れない。
「これは困った……」
迷っている内に日も暮れ出した。夜になれば山は真の闇となる。そうなれば、飢えた獣と共に夜を越さねばならない。如何に頼光が武勇の士とはいえ、都の者である。山で一夜を越せる知恵があるわけもなかった。
途方に暮れる内に、木々の隙間から差し込む光は紅く、心細くなっていく。濃くなっていく闇と、薄くなっていく光の――その狭間から、声がした。
「もし、お困りのようですが……」
頼光は目を凝らして見た。いつの間にか、光を背にして女が立っていた。
山の中だというのに真っ白い衣を身につけ、その下の肌も雪のように白く、そしてその髪もまた白い、全てが真っ白な女だった。歳の頃は若さの盛りを過ぎているというところだが、それだけになお、匂い立つような色気を感じさせる女であった。
――山姥。
頼光は直観した。元より、このような場所にこの時間、しかもこのような姿で現れるとは尋常のものではない。なにより、ただならぬ雰囲気をこの女は漂わせていた。思わず、腰に提げた太刀に手をかける。
「そう身構えますな。ただの山女でございますよ」
女はからりと笑ってみせた。都の女のように恥じ入るではなく、また村の女のように野卑て品のない笑いでもない。艶やかで鮮やかな、女の笑いだった。
「夜の山は危のうございます。幸い、わたくしの小屋が近くにありますゆえ、案内いたします」
「……」
頼光は太刀から手を降ろし、女の後についていった。この山姥を捕えるのは明日になってからでも出来る――そう思ったのは自身への言い訳だっただろうか。
* * *
女の小屋は川の近くにあった。粗末ではあるが小奇麗に片付いており、中に入ればそこが山であることを忘れるかのように、芳しい香りに満ちていた。奥の方には祭壇のようなものが設えてある。
「狭い所ですが、ごゆるりとお過ごしください。夜が明ければ、金太郎に里まで送らせましょう」
「……金太郎?」
「わたくしの息子でございます」
頼光が金太郎を追って道に迷ったことを知ってか知らずか、女はさらりと言った。頼光は戸惑った。その顔を見て、女は首をかしげる。
「そんなに驚かれましたか?」
「いや、その……それにしてはお主、随分若く見えるなと……」
「あら、これはどうも」
女はまた笑った。卑屈さの微塵も感じられない、軽やかな笑顔だった。唖然としてその顔に見とれていた頼光を、女が見つめ返す。頼光は慌てて咳払いをし、言葉を探した。
「そのぅ……そなたはここにずっと住んでおるのか?」
「金太郎が生まれてからは。その前は各地を渡っておりました」
渡り巫女――土地の社に属せず、各地を渡り歩く放浪の巫女である。都でもたびたび見かけることがあった。
渡り巫女は訪れた先々で芸をしながら託宣や祈祷などを行って回る。一方で、客と一夜を共にすることもあった。
つまり、そうして客を取っている内に子どもができ、ここに定住している、というわけか――あやかしでも、山姥でもない。しかし、渡り巫女や傀儡子といった放浪の民は、朝廷の律令を受け容れようとしない「まつろわぬ民」である。
「なぜこのような場所に? 里にも住むところはあろう」
この辺りの山では、そういったものが集まって山賊集団や反朝廷の勢力となっていることもある。だとすれば、頼光にとってこの女は「敵」だということになる。
女は鋭く問う頼光に微笑み返して言った。
「金太郎の父親がおりますゆえ」
「父親……?」
「はい。この山に棲む龍でございます」
驚く頼光に、女は語り始めた。