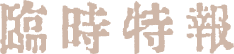ナチスの将校と青褪めた美少女の倒錯的な愛
―映画『愛の嵐』―暗い目をした女優・シャーロット・ランプリング―
上半身ヌードにサスペンダー、ナチスの軍服に身を包んだ退廃的なユダヤの美少女―。
若き日のシャーロット・ランプリングの代表作『愛の嵐』の
劇中の名シーンと物語、印象的な音楽についての雑記です。

淑女のみなさまこんばんは。
突然ですが、女にとって「幸せ」とはなんでしょう。
豪奢な生活と華やかな肩書きがあれば充分満たされる人もいるでしょうし、自己実現出来る仕事と面白い毎日さえあれば幸せ、という方もいるでしょう。
ある人から見れば不幸極まりなく、『あんなふうになるくらいなら死んだほうがマシ!』なんて思われる状況に一周まわって幸せを感じてしまうタイプの女性がいるのもまた事実です。
本人がそれを「幸せ」と自覚しているかはまた別ですが……。
「幸せ」のかたちは実に様々です。
それは、自分の価値観だけでなく、時代背景や状況によってどうにでも変容していく得体の知れないもの。
そもそも、”自分の価値観”というものほど移ろいやすく、自分以外の何かに左右されてしまうものはないかもしれないのです。
「幸せ」など、本当は実体などない薄羽蜻蛉のようなものなのかもしれません。
さて、映画『愛の嵐/The Night Porter』。
ルキノ・ヴィスコンティ監督の『地獄に堕ちた勇者ども』でも共演していたダーク・ボガード&シャーロット・ランブリングの共演作です。

支配・被支配の関係値における愛と破滅を描いた退廃的な物語、ともいえますが、あらゆるものを削ぎ落とし、純粋な「愛」を淡々と描いた物語のようにも感じます。
監督はリリアナ・カヴァーニというドキュメンタリー映画出身の女性監督ですが、ヴィスコンティの描いたあの仄暗く青褪めた、残酷な官能世界を好きな方ならこちらも絶対好きに違いありません。
舞台はナチス政権下のドイツ。
強制収容所に収監された美少女・ルチアは、死の香り漂う閉鎖された空間で、ナチスの将校たちに心も身体も弄ばれ支配されることで死を免れ、恐怖の時代を生き抜きます。

そして時代は1957年・冬のウィーンへ。
旧ナチス党員であり、高級将校であった過去を隠し、今は小さなホテルのフロント係をしているマクシミリアン(マックス)。
今は高名な指揮者の妻となっているルチアでしたが、偶然にもこのホテルを訪れ、いまや戦争犯罪人となったマックスと再会することになります。

問題のない結婚生活を送り、戦時下のように支配されることも辱めを受けることもなく、幸せなはずのルチア。
それなのに、なぜか夫を先に送り出し、ひとりホテルに残ってマックスの側にいることを選ぶのです。
劇中でルチアの夫が指揮するオペラ、モーツァルトの『魔笛』をマックスとともに聴くシーンがあるのですが、ここで歌われている二重奏の歌詞は、まるでふたりの過去と未来を暗示しているかのようです。
愛を知る男のひとは良い心も持っている
愛の心をともに感じるのが女性の一番のつとめ
私たちは愛を楽しみたい
私たちは、ただ愛によってのみ生きている
愛は苦しみを和らげ
生き物はみな愛に身を捧げる
愛が目指すのは男と女が最も尊いこと
男と女、女と男は神に近づく
―モーツァルト『魔笛』第一幕・パパゲーノとパミーナの二重奏より―
こうして、現在のシーンとそこにフラッシュバックしてくるかのようなナチス時代の映像が交互に場面転換され、失われた空白の期間を埋めるかのように愛欲の世界に没頭し、物語は悲劇的な方向に加速度的に進んでいきます。
無彩色に近いほど青みを帯びたフィルムは、シャーロット・ランブリングの蒼く灰色がかった瞳の色とあいまって、そのまま主人公たちの心象風景を表しているよう。

もうひとつ印象的なのは、ナチス時代、将校たちのおもちゃにされているルチアが歌う『何か望みを聞かれたら』という歌。
何が欲しいと聞かれれば、わからないと答えるだけ
良いときもあれば、悪いときもあるから
何が欲しいと聞かれれば、「小さな幸せ」とでも言っておくわ
だってもし幸せ過ぎたら、悲しい昔が恋しくなってしまうから
―映画『愛の嵐』劇中歌「何か望みを聞かれたら』―
まるで、大人になってからの自分の悲劇的な未来を予見するかのような歌です。
この時の”上半身ヌード×ナチスの軍服”のルチアはゾッとするほどの退廃美。
映画を観ていない人もこの衣装には見覚えがあるかもしれません。

シャーロット・ランブリングの痩せぎすの身体と暗い眼差しだからこそ醸し出せるセンシュアル。
いわゆる豊満なエロスでは到底醸し出せない、デカダンスな魅力がひたすらダダ漏れる名シーンです。
ルチアにとっての「幸せ」は、幼いころに身も心も支配し、それが結果的に自分を守ってくれたナチスの将校と、再び閉鎖された愛の世界に没入することだったのでしょうか。
たとえそれが”悲しい昔”だったとしても。
生と死の狭間、あまりにも激しい時代を生き抜いたふたり。
彼らにとっては、淡々と過ぎてゆく平穏な日々や、幸せを与えてくれる人よりも、死の香り漂う”閉じられた愛の世界”に再び生きることが「幸せ」だったのでしょう。

それにしてもシャーロット・ランブリングの暗い輝きを放つ瞳は、まさに退廃の国からやってきた美少女。
70年代にヴィスコンティのミューズとして活躍した彼女、その後は目立った活動がなかったような気がするのですが、50代を過ぎて出演した『まぼろし』以降、フランソワ・オゾン監督のミューズとなった彼女は、再び大人の女優として脚光を浴びています。
2016年公開のアンドリュー・ヘイ監督作品『さざなみ』では、女優デビュー50周年を過ぎて初のオスカーにノミネート。
年齢を重ねていても、あの青褪めた眼差しは色褪せず……
これからも素敵な作品を退廃的な魅力で彩って欲しい、大好きな女優さんです。