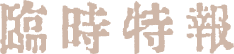「自分が今持っている能力の中で一番高いものを売ろう」と思った。
元デートクラブ嬢が当時の仕事の話する
今から数年前に、デートクラブの事務所の扉を叩いたのが、私がセックスワークの世界に飛び込んだ瞬間だった。
そのときの話をしようと思う。

ある日突然崩壊した日常
デートクラブというのは、分かりやすく言うと愛人の紹介所のようなものだ。
お金と余裕のある男性とお付き合いがしたい女の子たちが、小さな事務所に面接に行って、写真その他のプロフィールを作ってもらい、男性会員からの連絡を待つ。男性会員は、気になった女の子がいたら、置屋である事務所に紹介料を払って、女の子と会う。
ホテルのロビーなどで待ち合わせて、喫茶店や、デート向きのレストランで食事をしながら互いの話をする。場合によってはそのままホテルに行く。
お互いを気に入って、条件が折り合えば、2回目以降は事務所を通さずに、2人で会うことができる。
当時の私には、かなり年上の恋人がいた。
その恋人と付き合って数ヶ月経った頃、彼が軽い接触事故に遭った。けがはなかったものの、念のために精密検査をすると言う。
事故が大事にならなかった時点で、私はすっかりほっとしていた。精密検査の結果は予想外のものだった。
事故による後遺症はなかった。が、進行性の癌が見つかったのだ。
私の恋人はささやかながら事業をやっていて、貯蓄というものをほとんど持っていなかった。
当面の治療費が出せない、という理由で、頼られたのは私だった。
あまりにショックなことが多すぎて、私には冷静な判断ができなかったし、当時の私は月収が16万くらいで、そして曲がりなりにも東京で生活をしていた。
「自分が今持っている能力の中で一番高いものを売ろう」と思った。
年上の恋人に向き合うときに発揮しているそれを他の誰かに向けて、結果的に彼を助けられるなら同じことのような気がした。
風俗の世界へ
それでも、風俗の世界に足を踏み入れるのはとても勇気のいることだった。
当時住んでいた自宅からすぐの繁華街で、ソフトサービスを謳う店に面接に行ったときには、間髪を入れずに差し出された「オプションサービス一覧表」の生々しい内容と、「どこまで出来ますか」と問う面接担当者の光の差さないまなざしに恐怖を感じて、半泣きで帰ってきた。
デートクラブの面接は淡々としていて、性的なにおいがしなかった。世間知らずだった私は、その突き放した感じと、デートの相手と直接会ってその後どうするかを決められるスタイルに魅力を感じた。
会員になってすぐ、事務所が何本か紹介のメールを送ってくれた。私は片っ端から会うことに決めていた。合う人も合わない人もいたが、1回の食事でだいたい判断ができた。私の条件ははっきりしていた。月1ペースで会って継続的な関係を作ってくれること。1回のデートで4万円を渡してくれること。私生活に立ち入らないこと。ちゃんと避妊をすること。
多少の入れ替わりはあったが、月に3人ほどと継続的に会っていた。新しく会う人は、それとは別に毎月3人程度。昼間も仕事を続けていたのでそれなりに忙しかった。
私のお客さんはみなとても優しかった。
出張のたびに地方の美味しいものを買ってきてくれて、レストランやホテルのフロントではとても紳士的にエスコートをしてくれた。
私も精一杯それに応じた。
房総の海の見えるホテルに行ったときには、望まれた通りに笑って一緒に写真に写った。
彼らは驚くほど素直に、家族の話や仕事の話を私にしてくれた。
私もにこにこしながら話を聴いた。
彼らの日常から少しだけ浮いた、きらきらした日々のなかで、あたたかく柔らかい存在でいること。それが私の仕事だと思った。
彼らは圧倒的に悪意がなく、そして必死だった。そんな彼らに対して、彼女のふりをし続けている自分の方が汚れているように思えるくらいだった。
東京湾の夜景が見えるホテルで、もう何度も会っていたお客さんから「コンドームをつけないでセックスしたい」と言われたとき、私はやんわりと断った。
分かっていても言ってしまった、ごめんね、と肩を落として言うその人を見て、シンプルにかわいそうだと感じた。
その直前の瞬間に感じた恐怖と、その気持ちが不協和音にならずに、私の中で響き続けているのを不思議な気持ちで観察していた。そのお客さんとはそれきり会わなかった。
写真を何十枚と撮られたときには、笑顔を作りながら、自分の存在が幽霊みたいになって写真に捉えられなければいいのにと思った。
車で千葉から東京に送ってもらい、自宅に帰ってしばらくして私は房総で食べた美味しいものを全部戻した。
貝類にあたったのかも、それか長時間のドライブに酔ったのかなと思って自分を納得させると、本当に自分が少し透けてしまったような気がした。その3日後の夜には別の新しいお客さんと会った。
気乗りがしなかったが、仕事だと思っていたから、アポイントをキャンセルすることはしなかった。
仕事と演技と自分自身の境目に私は悩んでいたけれど、その悩みをまともに自覚する余裕がなかった。
>>次ページ:「この人達はただただ純粋な、彼女という存在が欲しいんだ」