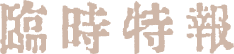山の子をその手に抱き、美しき山姥は笑う。
神々と寝た女 ~逢魔が時の過ぎぬ間に Vol.3 金太郎の母
「まさかりかついだ金太郎」――
彼がどうして生まれ、なぜ伝説になったのか、意外に知られていません。
金太郎は山姥と龍の間に生まれた子どもである、とする昔話が伝わっています。
その出生には、日本の成り立ちと山の民とに関わる、ある物語が隠されています。
近江の国の坂田郡に、山姥が棲んでいると噂されるようになったのはいつのころからだろう。
小一条の里の、湖と反対側にそびえる諸頭山に、それは棲んでいたという。
山に入った里の民が、美しい女を時折見かけるというのだった。
「あれは山姥だ。人を取って喰うに違いない」
「山姥などいるものか。逃亡した罪人の類であろう」
「しかし、この世のものとは思えぬ姿だというではないか。肌も髪も真っ白だというぞ」
人々は口々に噂をした。
男たちは山の天気を伺い、「山姥の機嫌がよくないようだ」と言い、猟の獲物を山姥のために残した。
母親は子どもに、「悪さをすると山姥がさらいに来るよ」と言い聞かせた。
この地を納めていたのは、鍛冶製鉄をその生業とした豪族・息長(そくちょう)氏であった。
京にほど近い長浜の地にあって、鉄をその手中に収めた息長の一族は、天皇家の外戚にも連なる有力豪族として勢力を誇った。
その息長氏の元へある日、都から武士がやってきた。
「朝家の守護たる摂津守どのが、どんなご用件ですかな」
一族の長は、目の前の武士に向かい、尋ねた。
摂津守、と呼ばれた武士の名は源頼光。
後世には、土蜘蛛や酒呑童子などの妖怪を討伐したと伝わる、武勇の士である。
「この山には霊気が満ちている、妖魅の類が棲んでいるに違いないと占術にて告げられた故に」
長は内心で舌打ちをした。
口実である。
源頼光は、「まつろわぬ民」――すなわち、朝廷に従わず野山に暮らす民を討伐することで手柄を上げてきた人物だ。
対して、鍛冶製鉄を生業とする息長氏は元来、山に暮らす民である。すなわち、出自で言えば朝敵たる「まつろわぬ民」に近い立場にある。それが権勢を誇っているのが気に入らないという者は、都にも多かった。
「山とは人の領域ではありませぬ。神々の領地、すなわち彼岸であります。魔物のひとつもおりましょう」
頼光は長の言葉を鼻で笑った。
「里の者の話では、山姥が棲んでいるというではないか。それも人を取って喰うのだという」
「ただの噂です。流れ者が棲みついているやもしれませぬが」
「もし朝廷に従わぬ咎人の類が山に棲みついているのであれば、狩り出さねばならないな。よもや止め立てはするまいな、長よ?」
長は眉をひそめた。立派な身なりをしたこの武士は、そうまでして手柄が欲しいのか。
しかし――息長氏や里の民の生活は今や、京の都あってのものだ。長はため息をついた。朝廷の意向に逆らうわけにはいかない。
「八幡宮から山へと入れば、鯉ヶ池という池があります。その辺りで見かけたという者がおります」
「なるほど。世話をかけた」
そう言って頼光は長の屋敷を後にした。
* * *

麓にある社から山へと入り、しばらく歩くと、澄んだ水を滔々と湛える池があった。ここが長の言っていた「鯉ヶ池」だろう。
頼光はその畔を歩んでいく。埃っぽい京の都とは違う、しっとりとした緑の風は艶めかしくさえあった。
「お侍さま、本当に山姥を捕えなさるので?」
里で案内に雇った樵が不安げに尋ねた。
「そうだ。朝廷に従わぬものを捨て置けぬのでな」
「あれはそんなもんじゃありませんだ」
「……お前は見たことがあるのか?」
「へぇ。祭りの日なんかには、里で見かけることもありますだ。真っ白な髪の美しい女ですだよ」
「人を取って喰うというではないか」
「はぁ、女ひとり山で暮らしているからには、妖(あやかし)かなにかではありましょうが」
頼光は樵の曖昧な返事にいらつきながら、山の中へと分け入っていった。
この土地に暮らす者にとって、山は生活の一部である。この案内人のような樵はもちろん、他の村人にとっても、猟の獲物や山の幸などの恵みをもたらしてくれる場であり、それと同時に畏れの対象でもあった。
電気などが発達する以前、道路が整備される以前のことである。山の闇は、昼でも深い。案内の樵でも、踏み込まない場所もあるのだという。
「……あれは?」
頼光と樵は同時に足を止めた。山の闇の中を、なにか大きなものが動くのが見えたからだ。
人影と見るには不格好で、頭が大きく不自然に揺れている。山に棲む動物にしては動きが緩慢に過ぎる。それは頼光たちが歩むけもの道の先を、横切るようにゆっくりと、動いていた。
木々の隙間から光が差した。
光に照らされたのは、うつ伏せになった熊の身体であった。それが宙に浮き、揺れながら山の中を行く――いや、よくよく見ればそれは、何者かが担ぎあげているのだった。
「あれは、金太郎ですわ」
樵が言った。
「金太郎……?」
「いつの間にかこの辺りに棲みついて、山で獲った動物や魚を村までよく売りに来るガキだでな。あの通り、熊まで仕留めおる……」
「ほう……」
その時、金太郎と呼ばれたその男が頼光たちの方へ振り向いた。ほとんど裸のような装いから真っ赤な肌が顕れ、その屈強な体躯を包んではいるものの、その顔はあどけなさを残した少年のものであり、背もまだ伸びきっていない様子だ。髪は乱雑に切り揃えてそのまま下ろしていた。
頼光はその少年に強く興味を惹かれた。この歳で熊をも仕留める剛の者である。
当の金太郎は、頼光たちを気にするでもなく振り返り、山の奥へと入っていった。
「おい、金太郎とやら、待つがよい」
頼光は金太郎の後を追い、けもの道をかき分けて駆け出した。
「お侍さま! あぶねぇだよ!」
樵のかける声は、森の闇に遮られたかのように頼光へは届かなかった。