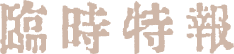女は「穢れ」なのか?
古典芸能のミカタ(第二回)ー伝統芸能と女性の舞台進出問題ー
大和撫子たるもの、日本文化・芸能を知らずしてどういたしましょう。
と、いうことで、カルチャー連載の名にふさわしい^ ^連載がスタート♪
案内役は、出版界きってのカルチャー男子でもある中井仲蔵パイセン。
歌舞伎・浄瑠璃・能・狂言・現代劇の舞台はもちろん、最新の公開映画から宝塚歌劇
まで、あらゆる舞台演劇エンターテイメントに精通している仲蔵さんだからこそ、
難解なイメージの古典芸能もライトな切り口でわかりやすくナビゲートしてくれるはず。
第二回目のテーマは、昨今ニュースでも話題の「伝統芸能における女性の舞台進出」についてです。

⇡神聖な土俵(両国国技館)。
大相撲の「土俵問題」っていうのが今、ちょっとした話題になっていますね。
よくは知りませんが、なんでも土俵ってのは神聖な場所で、女の人は医療関係者から市長、わんぱく相撲の小学生女子に至るまで「穢(けが)れているから」上がっちゃいけないって言うひとがいるそうです。
ぼく自身は、「21世紀にもなって、何をマヌケなこと言ってるんだか」と思ってますが、頑なに「それが日本の伝統なのだ!」と声高に叫ぶ人なんかもいたりして、問題はまだまだ長引きそうです。
さて、相撲関係者にとって土俵が神聖なように、演劇・演芸関係者には舞台は神聖な場所です。
そこで今回は、古典芸能の舞台にどれくらい女性が進出できているのか、見てみようと思います。
まずは落語界およびその界隈から。
現代でも寄席に行くと、落語家たちはみんな和服で、足袋のまま高座に上がります。雪駄や下駄などは履いていません。
一方で、漫才や奇術など色物の人たちはみんな洋装ですが、必ず靴を脱いで舞台に立ちます。
お暇があれば日曜の夕方に『笑点』(日本テレビ系)を観てください。
漫才師が登場する際は、必ず靴を脱いで舞台に上がってますから。
寄席の高座で靴のまま上がってもいいのは、タップダンスの芸人だけ。
タップシューズを履いて出演しています。
とはいえ、舞台の上に板を敷いて、その上で踊るので、土足で高座に上がっているわけではありません。
余談ですが、寅さんで有名な渥美清は浅草の舞台の出身ですが、彼が初めてテレビに出演した際、ステージの上で靴を脱いでしまったとか。
かように、寄席に出ている人々は、舞台に対して並々ならぬ敬意を抱いているんです。

⇡舞台から客席を眺めると…(国立劇場小劇場)
では落語界における、女性の進出度はどんなもんなんでしょうか。
結論から先に言うと、古典芸能の中では「女性の活躍が最も著しい」といえそうです。
テレビに出てくる噺家がお爺さんばかりなので、古色蒼然、因循姑息な世界を想像する人も少なくないでしょう。
でも、実際に寄席を訪れてみれば、若い世代の女性がめちゃくちゃ多いことに気づくはずです。
関係者によると、00年代の半ばに起こった落語ブームの影響か、昔に比べてやたら女性の入門者が増え、一時は前座の6割が女性だったとか。
考えてみれば、落語は座って話すのがメインの仕事。
使う道具は扇子や手ぬぐいのみ。
それより重たいものを持たないんですから、男性なみの筋力を求められません。そもそもお爺ちゃんになってもやれるくらいですからね。
話芸を磨けば、男女問わず成功するジャンルと言えるでしょう。
そんなわけで、寄席界隈では女性の社会進出は著しいと言えますが、ただし、女流の噺家には一つだけ大きく不利な点があります。
というのは、いわゆる「古典落語」と言われる演目は、古来、男が演じるために作られ、さまざまな男の落語家たちに継承されつつ改良されてきたものだからです。
そもそも女の人が演じることを想定されていないので、演出や台詞を変えずにそのまま高座にかけると、客は何だかよくわからなくなってしまって笑えなくなることがしばしばあります。
それを踏まえ、たとえば桂右團治や桂吉坊などは、宝塚の男役みたいに、高座では完全に「男」として振る舞うことで、そのジレンマを解消しようとしています。
一方で桂あやめや川柳つくしなどは、自分の寸法に合ったオリジナルの噺を自分で作り、それを高座にかけています。
いずれにせよ、女の演者がますます増えることで、今後の落語は、さまざまな面で大きく変わっていくことでしょう。
さて、お次は歌舞伎ですが、これは江戸時代に、お上から「公序良俗を鑑みて、女が舞台に上がってはならぬ」というお達しが出て以来、男の役者だけが出演する演劇として発達してきました。

⇡揚げ幕の中にも座席があった平成中村座
市川海老蔵の妹の市川ぼたんや、尾上菊之助の姉の寺島しのぶは、いずれも歌舞伎の名家に生まれた芸能人ですが、歌舞伎役者として舞台に立ったことはありません。
そんなわけで歌舞伎の衣装や演出は、役者に男の体力があることを前提に作られてきました。このへんの事情は、ちょっと落語と似てますね。
アダな年増も、可憐な乙女も、化粧と衣装を剥げばスネ毛の生えた筋骨たくましいオッサンが演じることになります。
演目によっては、美しい衣装を何着も見せるための早着替えが欠かせないのですが、普通ならとても動けないくらい重たい衣装を何枚も重ね着することもしばしばあります。
そんな状態で、さらに動き回ったり踊ったり見得をしたまま静止したりするわけですから、谷亮子や吉田沙保里のようなアスリートならともかく、並の女優には務まりません。
その結果、「女形(おんながた)のほうが、立役(たちやく=男役のこと)の何倍も筋力がいる」とまでいう人もいるくらいです。
現代も女性が歌舞伎役者になれないのは、そういう体力的な理由もあるようです。 ただし、舞台上にまったく女性がいないかといえば、決してそういうわけではありません。
歌舞伎の作品はほとんどがミュージカルなので、かならず楽器演奏が入るのですが、かなりの数の女性がそれに携わっています。
多くの場合は、御簾(みす)に隠れて見えない位置にいますが、箏(こと)を使う演目のときは、女性がたくさん、舞台に堂々と楽器を並べて演奏する姿が見られます。
また、幼いときは男女に体力差もないせいか、子役も半分くらいが女の子という印象です。
もちろん、大通具や小道具や美術や衣装などの裏方にも女性はたくさんいます。
演技をしている大人は男ばかりですが、女性がいなかったら、舞台は立ち行かないことでしょう。
いちばん女性進出が遅れている古典演芸のジャンルは、人形浄瑠璃(文楽)かもしれません。
文楽の演者は、物語を節に乗せて語る「太夫」、その伴奏をする「三味線」、そして3人で一つの人形を操る「人形遣い」の3業に分かれていますが、公益財団法人文楽協会に所属する八十数名の技芸員の中に、女性は一人もいないのです。
これは、文楽が人形劇だという側面が大きいようです。
一度持ってみれば分かりますが、文楽の人形はけっこう重いうえに、3人がかりで操るため、力がない人や、体のサイズが小さい人には扱いづらいのです。
歌舞伎の女形同様、体力がものをいうわけですね。
残り2業の、太夫と三味線ならどうでしょうか。
重たい物を持ち上げるわけではないから、女性でもできないことはありません。
という発想で作られたのが、女が三味線に合わせて義太夫を語る「娘義太夫」(または「女義太夫」)というジャンルです。
これは、人形浄瑠璃から人形を抜いたものといえばわかりやすいでしょうか。
人形は出てこず、落語や講談のように演者が語りと三味線だけで聞かせる芸です。
誕生は江戸中期で、最盛期は明治時代だったそうですが、今でも根強いファンがおり、定期的に公演が行われています。
NHK朝ドラ『わろてんか』にも、広瀬アリス演じる女義太夫が出てきたので、ご覧になった人も多いのではだいでしょうか。
スポーツの競技が男子と女子に分かれているように、これも同じ芸能が男女で分かれ、住み分けされているわけですね。
余談ですが、ビートたけしのお祖母さんは娘義太夫をやっていたそうで、たけし軍団の「グレート義太夫」という名前はそこからとったとか。
最期に、相撲と同じく「神事」という面も併せ持つ「能楽」を見てみましょう。
神社やお寺の境内に能楽堂があることが多々ありますが、能もやはり「神様に捧げる芸能」とされています。
相撲における土俵のように、能舞台は神聖視されており、舞台上でツバを吐くなど、神様に失礼な行為はご法度。
おかげで能楽堂はどこも、厳かな雰囲気が充満しています。
観客の方もその空気に飲まれ、みんなかしこまって観ています。
同じ神事を名乗っていても、食べたり飲んだり座布団を投げたりしながら観戦できる相撲よりも、断然厳しいといえそうです。

⇡厳かな雰囲気の能楽堂の舞台
そんな神聖な能舞台に、女性が上がってもいいものなのでしょうか?
……それがまあ、どうやら何の問題もないみたいです。
実際に能を観に行くと、舞台上にいるのは圧倒的に男が多いとはいえ、女性も出ていないわけではありません。
ちょっとネットで見てみると、社団法人能楽協会の会員約1400人のうち、約200人は女性なんだとか。
7人に1人はまだまだ少ないともいえますが、これは国会における女性議員占有率(10.1%=2017年秋の衆院選終了後)より断然多い割合でしょう。
相撲並みに古く、相撲同様に神事とされている能楽ですが、「女は能舞台に立つな」なんてタワゴトは、その界隈では聞かれないようです。
以上、古典芸能をいろいろ眺め回してみました。
あくまでもぼくが部外者として外から眺めているだけなので、現場で働く女性たちからすれば「実際はゴリゴリのセクハラが横行するブラックな職場環境なのよ」という可能性もないわけじゃないのかもしれませんが、いずれにせよ「穢れ」を理由に理不尽な性差別が横行する世界ではなさそうです。

⇡ストリップは女性がいなけりゃ始まらない?